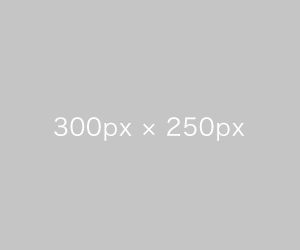父親自身も苦労の人生を歩んできた。パキスタンで大学教育を受け、その後パレスチナで空港のエンジニアとして働いていたが、爆撃で職場を失った。日本で大学院生として学び直し、現在はドバイで大学教授として成功を収めている。「貧乏生活からドバイドリーム」。月10万円の奨学金で家族4人が暮らしていた日本時代から、現在では家も購入し、車も複数台所有するまでになった。まさに「ドバイドリーム」を体現している家族の物語だ。
就職活動と将来への不安
現在、大学卒業を控えて将来への不安を抱えている。ドバイでは日本のような一斉就職活動のシステムがなく、多くの学生がインターン先にそのまま就職するパターンが一般的だという。しかし、彼女のインターン先では「新卒の人が誰一人いない」という状況で、採用の見込みが不透明だった。
一方で、ドバイで活躍する多くの起業家や挑戦者を見て、「個人で何かをやっている」道への憧れも抱いている。「自分で会社を作ったりとか」。就職という安定した道を選ぶか、リスクを取って独立の道を歩むか。この選択に迷いを感じているのが現在の心境だ。
興味深いのは、働くことに対する価値観の変化だった。「会社員になるのは絶対に嫌だと思っていた。働きたくないし、楽しくないものだというイメージがあった」。しかし、実際にインターンを経験してから考えが変わった。「インターンに入ってから、会社が良すぎて。これもありかなと思っている」。良い職場環境を実際に体験することで、会社員という働き方に対する偏見が取り除かれたのだ。
アイデンティティの探求と唯一無二の存在
「何人?」という問いへの答え
インタビューの冒頭で投げかけられた「何人ですか?」という質問は、彼女にとって最も答えにくい質問の一つだった。「難しい。結構結論が出たことがない」。彼女が考えるのは、国籍や血統ではなく、「どこが1番居心地がいいかな」「何人としてが1番居心地がいいかな」という実存的な問いだった。

「半分パレスチナ、半分日本みたい」という表現で一応の答えを出しているが、それでも明確な結論には至っていない。興味深いのは、赤ちゃんの頃から「日本人」と呼ばれていた話だ。「肌が白くて、ちょっと黒髪だったから、寝る時とか子守唄を歌う時に、日本人よ眠れみたいに言われていて、そしたら本当に日本人の国籍になった」。母親が無意識に歌っていた子守唄の歌詞が、まるで予言のように現実になったという不思議な話だ。
海外に出る日本人へのメッセージ
インタビューの最後に、海外に出る日本人に向けて重要なメッセージを送った。「海外もすごく素晴らしいし、日本もすごく素晴らしい。でも日本らしさを忘れず、海外に来ても忘れずに過ごしてほしいと思う」。
特に強調したのは、無理に現地に合わせようとする必要はないということだった。「時代に合わせようとしたり、外国人の真似をしたりしなくても、本当に日本の良さを活かしながら楽しめればいいかなと思う」。この言葉は、多文化環境を実際に経験し、様々な価値観に触れてきた彼女だからこそ言える、深い洞察に基づいたアドバイスだ。
彼女自身の経験を振り返ると、日本で培った価値観や文化的背景が、海外でも彼女の核となる部分を形成していることが分かる。料理の好み、マナーに対する感覚、時間に対する考え方など、根本的な部分では日本文化の影響が色濃く残っている。
現在進行形の物語
現在は、ドバイの一流企業でインターンとして働きながら、将来の方向性を模索している。職場環境への満足度は高く、「これもありかな」と就職への前向きな気持ちも芽生えている。
大学卒業を控えた現在、彼女は人生の大きな転換点に立っている。これまでの人生が常に移動と適応の連続だった彼女にとって、ドバイでの定住は新たな挑戦かもしれない。しかし、これまでの経験を考えれば、どのような道を選んでも彼女なりの答えを見つけていくだろう。爆撃の中で生まれ、貧困を経験し、言語の壁を乗り越え、文化の違いを受け入れてきた彼女には、どんな困難も乗り越える力がある。
多様性の時代を生きる意味
インタビューを通じて浮かび上がったのは、「唯一無二」という言葉で表現された、独特なアイデンティティだった。パレスチナにルーツを持ち、日本で教育を受け、ヨルダンで苦労し、現在ドバイで活躍する彼女の人生は、確かに他に類を見ないものだ。国籍や血統、文化的背景のどれか一つでは定義できない、複雑で豊かなアイデンティティを持っている。
彼女の物語は、グローバル化が進む現代において、アイデンティティとは固定されたものではなく、様々な経験と選択によって形成される、流動的で多面的なものであることを教えてくれる。「何人か」という問いに明確な答えを出すことよりも、自分らしく生きることの方が大切なのかもしれない。
戦火から始まった彼女の人生は、今ドバイで新たな章を刻んでいる。どの国にも完全には属さない代わりに、どの国の良さも理解し、活かすことができる。それこそが、現代を生きる私たちにとって最も価値ある能力の一つなのではないだろうか。